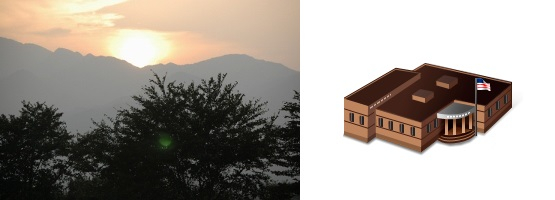【第354回】 “和”な一日道上 ちひろ (英語)
先日、本校茶道部は21世紀美術館にある、松涛庵というお茶室での催し「茶菓と箏曲を味わう」に参加した。
そこでは、本校の土曜講座(遊学講座)のお箏の先生である、北村愛里先生が和服姿でお箏を奏で、茶道部員は、大島宗広先生のご指導のもと、お抹茶と秋を表現したお菓子で観光客の方などをもてなしました。
秋晴れの金沢で、目で和を感じ、耳で和を楽しみ、口で和を味わう。秋を感じさせる、紅葉やとんぼの茶器やお菓子、お抹茶の味、そしてお茶室に響くお箏の音色。金沢で生まれ育った私ではあるが、初めての経験でした。まさに日本の美を五感で感じられる一日でした。
このようなことを言うと、私が、いかにも日本が大好きで、日本の和に詳しい金沢女性だと想像するかもしれない。しかし実はそうではない。むしろ“和”からはほど遠く、西洋のものやモダンなもののほうが、だんぜんお好みの私である…。
そんな私が、日本文化の素晴らしさや、金沢という町の良さを純粋に感じることのできる貴重な経験となった。
お茶会が終わったとき、生徒が「あー、楽しかったぁ」と、一言。それを聞き、この和を愛する女子高生は、将来きっと、“すてきな金沢小町”になるのだなぁ、と、ほんわかした気持ちになれる一日でした。