【第379回】 考えることO. M. (国語)
その昔、フランスの思想家で哲学者のパスカルは自分の著作『パンセ』の中で、「人間は考える葦(あし)である。」と言いました。葦とは川辺に生えている雑草のことで、強い風が吹くとすぐに根こそぎ倒れてしまいます。パスカルはこの言葉で、「人間なんて所詮、川辺に生えている弱い雑草のようなものだ。」「でも、人間は考えることが出来る。川辺の雑草と違うところはそこだ。」と言いたかったのでしょうか。それならば、考えない人間は川辺の雑草と同じだということですよね・・・。
私たち庶民(一般ピーポー)は、往々にして「考える」という作業を放棄してしまうことがよくあります。「面倒くさい」・「考えても答えが出ない」・「わからんし!!」こんな理由をつけて、考えないという行為を正当化して、真剣に考えて、悩んでいる人に向かって、「あんまり考えすぎると体に毒だよ・・」などと言い、あたかも考えないことを健康的で、楽天的に生きることが素晴らしいみたいに語ろうとする風潮はないでしょうか。そして、そんな気の利いた逃げ言葉に私たちは踊らされてはいないでしょうか。
遊学館高校の生徒は、とても素直で純粋で、勉強したいという気持ちを持った高校生が大勢います。しかしその反面、(これはもちろん全ての高校生に通じることですが)「考える」ことをあきらめて、「わかったふり」・「知っているふり」・「考えるふり」をして、それを誰にも悟られないように隠しながら、授業時間が過ぎていくのをじっと待っている人たちも中にはいます。おそらくそんな人たちは、授業時間が退屈で、ひまで、だから眠たくてしょうがないのではないでしょうか。
先日1年生の古典の授業で、あえてグループになって、漢文の訓読の練習を初めてやってもらいました。わからないところは仲の良い友達と相談できるし、みんなで考えて悩んで答えをひねり出すことができます。おかげでこちらが答えを言う前に、自分達で解答を見つけ出すことのできた、とてもいい授業になったと思いました。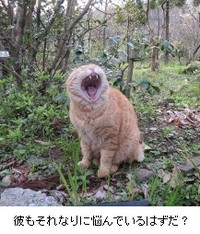
高校生活の3年間なんて、あっという間です。社会に出れば、想像もできないくらいの大変なことが山のように押し寄せてきます。そんな時、お金も無い、社会的な力も無い若い人に出来ることは、有り余る体力と、有り余る時間を精一杯使って「考え・悩む」ことだと思います。「グズグズ考える」「クヨクヨ悩む」そうして自分なりの答えを見つけ出していく・・・。
そんな時間の重なりが、複雑怪奇、ぐっちゃぐちゃに入り組んだこれからの世の中を渡っていくための最終兵器になるんじゃないかな~と、今日もクドクドと考えています。
