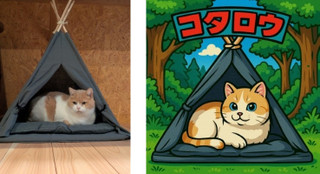【第886回】「そこの3年生、「カフェテリア履修」って知ってる?」尾谷 力 (地歴・公民)
先日、金城大学で行われるオープンキャンパスに参加してきました。この行事は3年生の担任を務める私にとって楽しみな行事の一つです。理由は3月に卒業した卒業生たちの少し成長した姿に会えるからです。
さて、3年生の皆さん、金城大学短期大学部ビジネス実務学科の「カフェテリア履修」を知っていますか?
高校3年生という年代は微妙な年齢だと思います。すでに成人に達している人もいます。かといって18年間の経験で人生を左右する進路選択を決定するには、心配事もあるはずです。そこで私は「カフェテリア履修」こそ有効だと考えます。
「カフェテリア履修」とは自分の必要と考える講義をカフェで注文するように選んで学べる、進路目標の決まっている生徒は勿論、明確な目標の見いだせない生徒にとっても有効な学び方です。準備されている講義は、例えばパソコン操作に加えて、メイクやネイル、サブカルチャー、栄養や英会話、接客など様々で、それらを自由に選択し幅広く学ぶことができます。(このシステムは県内の他の短大にはありません。)
その結果、進路決定を短大2年生まで伸ばせます。その分、経験を重ね自分を確立した上で進路を決めれます。それは選択ミスのリスクを抑えることに結びつきます。さらに異なる業種のスキルも身に付けることができ、選択の幅を拡げることも可能となります。
人生とは選択の連続、そして選択の積み重ねです。もし今、重ねるべき選択が見つからないなら焦らず「カフェテリア履修」を選択するのもいいのではないでしょうか。
卒業生たちの「金城大学でよかった」、「新しい友人ができた」、「バイト始めたよ」などの誇らしげな報告に元気をもらい、今年も3年生の担任を味わいたいです。