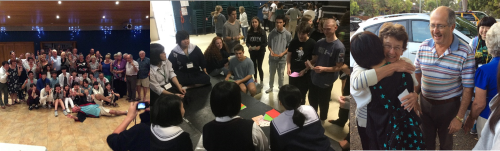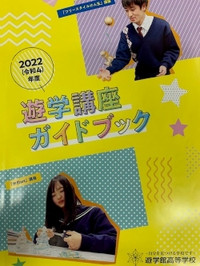【第761回】「知識のクーポン券」T. Y. (国語)
最近、電子書籍を読む機会が多くなりました。
電子書籍アプリには様々なジャンルの本が並んでいます。普段なら絶対手に取らないバスマガジンという本を開いてみました。
私はバス通学もバス通勤もしたことがないので、ほとんどバスに乗ることはありません。
しかし、表紙が地元の新潟ということもあって興味本位で開いてみました。
そこには、ほんとにバス好きのためのバスの細かい歴史や情報が詰まっており、面白いかと言われれば二回は読まないかなという感じです。
そこで得た知識が今後バスを乗らない自分の役に立つのかはわかりませんが、知識のクーポン券としてバスの話題が出た時には使えるだろうとストックしておきます。
学校では様々な情報や知識を仕入れることができます。
仕入れた情報がいつどのように使えるのかはわかりませんが、いざ使うときに「あのクーポン券どこいったかな」とならないように、頭の記憶容量を増やすことが大事です。
この雑多なクーポン券をたくさん持っていることで、私自身もコミュニケーションツールとしてお得に使えた経験もあります。
しかし、このクーポン券が使えるような場所に行かなければ使えないし、いつどのようなタイミングで使えるのかはわかりません。
使用期限はありませんので、たくさん持っていて得はあっても損はないと思います。
ただし、偽物のクーポン券も世の中にゴロゴロあるので、真贋はきちんと確かめた方が良いでしょう。