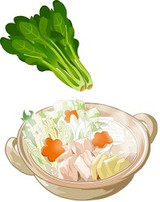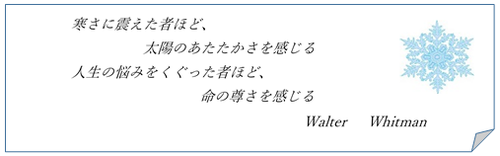【第669回】 「初めての冬」K. R. (地歴・公民)
2020年8月22日、錦町に人工芝のサッカーグラウンドが完成し、「竣工式」が行われた。
「自分たちの専用グラウンドができとことに常に感謝を忘れず、行動で表現していこう」
と選手たちに伝えた。
「感謝を表現する」とは、試合結果やチームの練習前後のグラウンド清掃だけでなく、各々が学校生活でも感謝を表現していこう、とも伝えた。
約4か月後、錦町グラウンドは初めての冬を迎えた。
この冬、石川県内の天気予報は「雪」マークが多かった。
人工芝は地面の熱が伝わりづらいため雪が溶けにくく、また雪掻きをすればするほど、芝の痛みが早いとも聞く。
「初めての冬」に備えて、100mのブルーシートを10枚購入し、敷いてみることにした。水を撒いたり、ブルーシートの上を雪掻きしたり…。
「警戒レベルの寒波到来」というフレーズがニュースで流れるたびに、サッカー部のスタッフは朝、昼、夜と時間帯を決めて、手作りのホースで水を撒いたり、ブルーシートを引きなおすためにグラウンドへ向かった。
 |
 |
 |
ブルーシートをはがすと、綺麗な人工芝が見える。
初めての冬を乗り越えた錦町グラウンド。
あの大雪を乗り越えたグラウンドが逞しくも思えた。
雪の中、選手たちも私自身も「感謝」忘れずに一生懸命に練習に励み、
この錦町グラウンドのように、どんな苦難も乗り越えて強く逞しく戦っていきたい。
 |
 |