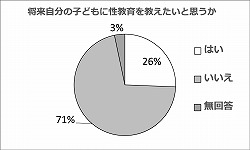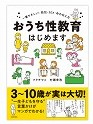【第746回】「遊学館高校 理科部の活動」T. M. (理科)
毎週、火曜日と金曜日の授業後、理科室で活動中です。
大きなイベントは春と秋の年2回、理科部総合文化祭行事として『高校生のための実験・実習セミナー』が行われることです。 春の内容は小松市にあるサイエンスヒルズこまつで普段、できない実験を行ったことです。今年は四ケ浦 弘先生による石英の石同士を勢いよく擦り合わせることで発光する現象実験、また蓄光テープにブラックライトを当てるとその後、光続ける現象など、40歳を過ぎた私も知らないことが連続の実習が行われました。
夏休中には金沢工業大学で水蒸気蒸留を使ってオレンジの皮から「リモネン」、クスノキの葉から「カンフル」を抽出する実験を行いました。顧問としては遊学館にはない実験器具での実験体験なのですごく有難い事です。
理科部の活動は生徒中心でやってみたい・作ってみたいことをやっています。
ペットボトルロケット作成・リヒテンベルク図形作成・ゴミ袋の熱気球の作成・ゾウの歯磨き粉実験・アンモニアの噴水実験・テルミッド反応など生徒から意見を挙げられ、現段階ではペットボトルロケット作成・リヒテンベルク図形作成とゴミ袋の熱気球の作成が達成されました。
魅力を感じたり、興味を持った生徒は是非、理科室を覗いてみてください。
2022年度の文化祭ではリヒテンベルク図形作成を無料で体験できます。(人気があれば毎年やります。)
下の写真にあるリヒテンベルク図形は木に強い電圧を与え、木目や細胞壁を伝わって火花が移動してできた模様です。同じ図形は出来ないのでオリジナルです。
楽しい実験だけが部活ではないので時には、データを出すために何度も同じことをしたり、自分の意見を発表する場合もあります。顧問としての技量の少なさを感じることもありますが、生徒と二人三脚で頑張っています。
 |
 |
|
| ↑石英の発光 | ↑水蒸気蒸留装置(オレンジの皮からリモネンの抽出) |
 |
| ↑リヒテンベルク図形・・同じ条件で電圧を与えたものですが、同じ模様がないのが特徴です |